第四の主人公がある意味、真の主人公?

RPGと勢力抗争の融合―――普通のRPGとは一線を画した幻想水滸伝の3作目。
プラットフォームがPS2に変わり、様々な新要素が加わりました・・・・・・そして共に、評価がかなり分かれたのも事実。
いったいどのような作品に仕上がったのか、少しずつ見ていきたいと思います。
まず、これまで平坦2D・・・・・・ある意味SFCレベルのグラフィックだった前作から、SD立体ポリゴン描写に一気に様変わりしました。この点で面食らうかも。
描写としてはデフォルメ重視。3〜4頭身が中心で、ワイルドアームズ3に近い雰囲気だと思えばいいです。
またイベントでは表情に喜怒哀楽がハッキリわかるぐらい変化し、詳細描写に一役買っています。
移動時は動かすうちに、自然自然と視点や背景が動いていく感じ。
これは賛否両論分かれたところで、いわゆる「世界に入り込んでいる」印象を受ける一方、特に視点が動いていくうちに進行方向も変化し、その度レバーを別方向に押さなければいけない点で、慣れない内は煩わしく思えます。
コレを解消するために、移動時はコントローラーのアナログレバーを駆使する事をオススメ。
一連のグラフィック関連の変化は酷評している人も多いですが、自分としては「慣れれば何とかなる」レベルかなぁ、と。
これまでの味気ないグラフィックに比べれば、イベント時に表情から仕草から、くどくない程度に動くようになったのは好感がもてますし。
視点変化による強制進行方向変化、ぐらいですかね。眉をしかめたのは。
さて、今回も仲間だけで100人余。
膨大なキャラの織り成す群像劇が描かれるわけですが、基本的には、これまでの雰囲気を踏襲しています。
避けられぬ別れ、プレイヤーを敢えて突き放す展開等、以前はスクウェアのお家芸だった特色は、この幻想水滸伝シリーズに受継がれた印象。
トーマス編以外は基本的にシリアス一直線。時々、コミカルな台詞回し―――特にゲド編のエース関連(笑)―――のギャップを楽しめるところもありますが、全体としての作風は「重い」です。
お気楽に楽しめる、って事はできないんですが、ハマればかなり深いところまで行く事が出来ます。
固定ファンが多いのも、こういう作風だからでしょうね。
システム面で大きく変わったのが二つ。
まずフィールドの概念ですが、マップ上は目的地までカーソル移動。で重要地や、道分岐の街道等が一種の戦場フィールドになっていて、そこでは実際に歩いたり、敵と戦ったりする方針です。
画面表記はやや違うのですが、基本的な枠組みはロマサガシリーズを思い出してもらえるとわかりやすいかと。
でまぁ、これが叩かれている要因でもありまして。
ダンジョンはいいとして、問題なのは街道分岐な方。グデーっとだだっ広いところで迷う事もあり得ない、ただ進むだけのところなのに、街から街(城)へ移動するたびにそこを歩かなきゃなりません。
最初のうちはそうでもなかったんですが、幾度も同じところを行き来するため新鮮味が無く、流石に後半になるとうっとうしくなります。
おまけに今回は「テレポート」の使える期間がかなり短いし・・・・・・。
もう一つが戦闘関連。
キャラ成長に数値的なもののほか、「スキル」と呼ばれる技能付与がついた事。バディと呼ばれる二人一組×3のパーティ編成になったこと。
前者に関しては間違いなく成功していると思います。各キャラでスキルストックの数が様々な上、その得意分野もかなり違います。
スキルの覚え方、組み合わせ方によっては大化けするキャラ(特にジョアン、フレッド)がいて、各種指南所でどれを覚えさせるかの取捨が楽しいところ。
一方の後者は・・・・・・大失敗(汗)。
おそらく集団線を意識したシステムにしたかったのでしょうが、一人一人に細かい指示が出来ない上、キャラによっては思うような行動をしてくれない場合があります。
特に魔道士系キャラ(杖装備)は、ほとんど物理攻撃に参加してくれないため―――少なくともザコ戦での―――キャラとしての重要性が一気に低下しました。
その他の基本的な部分は、前作を踏襲しています。レベル差で変わる経験値や、武器の改造、交易品、掘り出し物etc・・・・・・。
あ、もう一つ特筆するところ。今回のミニイベントとして加わった「劇場」。これはかなり面白いです。
演劇の配役を、仲間内から決めて演じてもらうんですが、キャラによって相当のバリエーションがあり、短いながらも反応が楽しみに。
特に、敢えてメチャクチャな配役にすると、セリフが繋がらないわ、妙ちきりんなセリフを吐くわで。様々な配役を試す価値はあると思います。
さて最後にその他の苦言。
そろそろバックボーンをハッキリさせてくれませんか?
3作目になるのに、そして、真の紋章の由来、各国間の位置付け(特にハルモニア)など、ストーリーの中でキーワードがいくつも出るにも係わらず、それらの説明がほとんど無い場合が多いため、とにかく消化不良の感が強い。
謎を引っ張りたい部分もわかりますが、「単品でプレイしている」人の事も考えて、もっと情報をオープンにすべき。
真の紋章に関しては、今回扱いが軽いのも疑問。世界の根幹に関わるもの(らしい)でありながら、今回はポンポンとあっちいったりこっちいったり(笑)してしまいます。
前作、前々作で紋章に囚われた者を描いているんですから、このへんはもうちょっと一蓮托生的な位置付けの方がよかったんじゃないでしょうか。
次に本拠地について、
トリニティシステムと呼ばれる、三者三様の視点から描く前半部分は十分に「アリ」だと思いますが、彼らがとりあえず手を結んだ後半部分、他の二人を同一パーティに組み込めなかったり、またまた別々のパーティで動かしたり、何よりそこからのストーリーボリュームが少なかったり、と・・・・・・。
最初は枝葉だった者達が、ひとつところに集まり大きな流れを作る―――そういう醍醐味が薄いですね。
3勢力が集まったら、あれ、あれれ??という感じでラストを迎えてしまいますから。
もう少し、後半のボリュームを増やすなりして、一体感を濃密に味わえる時間を多くとって欲しかったな、と。
あぁ、本当に長くなってしまった・・・・・・作風として独特であるし、魅力的なところもある、けれども指摘したいところも盛りだくさんだった、という事で。
今作は、これまでのファンであればあるほど、評価が低くなってるような気がします。
ただし、文句無しの傑作とは言え無いものの、決して駄作、クソゲーの類ではない、これは言っておかないと。
ファンの方が勝手にコアになってしまい、必然的に高いレベルを求め過ぎるようになった、そんなところから酷評が多くなってるんでしょう。もちろん、それに応えるべき努力もメーカー側に必要なんでしょうが・・・難しいシリーズになったもんです、ハイ・・・・・・。
私の場合、シリーズにものすごく思い入れがあるってほどではないんで、イチソフトとしてみた場合それほど悪い印象はありません。
オススメ度は、今作から入るならA、前作からならB、ってトコですかね。
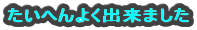
・三者三様のトリニティシステム。
・スキルの組み合わせにより、育成の楽しみが広がった。

・ストーリーボリュームが(特に後半)薄い。
・戦闘システムに煩わしいところアリ。
戻る
